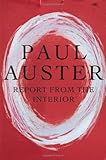以前Paul Austerの自伝「Winter Journal」を紹介しましたが、第二弾として出版されたのが本作「Rreport From The Interior」です。前者が外面的、後者が内面的自伝として一対になっています。
実はこれを読む為にKindle Paperwhiteを買ったんですが、先に「Winter Journal」を読んだ関係で今頃になってしまいました。
で、読了直後の印象としては、
「う~ん、なんじゃこりゃ?」
と呆然とした、というのが正直なところです。終わり方がとんでもなかったというところで余計にそう思うのかもしれませんが、「Winter Journal」がかっちりとした自伝だったのに比べると、随分奇抜で大胆な構成・内容となっており、しかもそれが必ずしも成功しているとは言えず、やや散漫な感が否めません。まあポール・オースター・ファンには興味深い作品には違いないのですが。。。
ちなみにKindleだと730円、ハードカバーだと2282円、やっぱりKindle買っといてよかったです(笑。
さて、四部構成となっている本書の題名と内容をざっくりと説明すると
第一部: Report From The Interior ; 幼少期から思春期前までの(内面的)思い出
第二部: The Blows To The Head ; 衝撃を受け人格形成に影響した映画二本の説明
第三部: Time Capsule ; 元妻Lydiaから送り返されてきた、大学生時代に彼女に送った手紙の開陳
第四部: Album ; 一から三部までの内容に関連した写真集
ということになります。
まあ、普通に自伝と呼べるのは第一部だけでしょう。文体も「Winter Journal」を踏襲しています。
第二部はほとんど映画の紹介、詳細は後で書きますが、個人的にはオースターの映画評論が好きなので、これが一番面白かったです。
第三部に至っては、内容は結構濃いものがあるのですが、よくもまあ恥ずかしげもなく昔のラブレターを開陳するものだなあ、と。特に最後の長大な一通は面白いけどひどい。
第四部は写真集ですから、これまでのエピソードに関する写真の数々を楽しめて一種のクールダウン、リラグゼーションにはなっています。
というわけで、まあポール・オースターのファン、あるいはアメリカ現代文学・現代史を勉強する方々専用の本だと思います。柴田元幸先生、いつかこの奇矯な自伝も邦訳されるんでしょうけど、苦笑いされる先生の顔が目に浮かぶようです。
さて、では内容のレビューに参りましょう。
Kindleの第一ページにはただ一行
「REPORT FROM THE INTERIOR」
とだけ書いてあります。普通これだけだと本の題名だと思っちゃいますよね。
そして前作と同じく自らを「You」という第二人称で語り始めますので、てっきり今回もこの文体で全体が貫かれると思ってしまいます。Kindleだとぱらぱらとめくって全体を俯瞰するわけにもいかないし、見事だまされてしまいました。
さて、この第一章、先ほど述べたように幼年~少年~思春期前期の思い出や子供なりの内面的思考が、1950年代の世相を背景に描かれます。大好きだった野球のこと、読んだ本、観たTV、映画、サマーキャンプ等いろいろな話題について、それぞれに面白いエピソードもあります。
有名な野球選手が家に来てくれるという期待感とその結果のがっかり度、H.G.ウェルズ原作のカラー映画「The War Of The World(邦題:宇宙戦争)」のわくわく感、子供時代のオースターをずっと悩ませていたおねしょを見事にサマーキャンプでやらかした時のこと、Junior Highに上がってからのKarenという女の子とのダンスのこと、などなど。
しかし、この章で一番心に残るのは、子供心に自分が「ユダヤ人」であることを自覚していく過程でしょう。当時のアメリカでのユダヤ人差別のみならず、オースター家がユダヤ人コミュニティの中でも疎外されていた、あまりユダヤ教の熱心な信者でなかったことなど、子供心にも自分のアイデンティティとしてのユダヤ人を意識せざるを得ない環境についてかなり詳しく語っています。
たとえば、小学校の頃「Jewboy」「Jew shit」とからかわれたオースターは、学校でクリスマス祝賀会へ出席してクリスマスキャロルを歌うのを拒み、教師の指示でひとり教室に残されます。突然静寂に包まれた部屋に時を刻む時計の音だけが響く。その教室でポーやスティーブンソン、コナン・ドイルを読むポール少年。その時の矜持を現在のポールはこう語っています。
「 a self-declared outacast, stubbornly holding your ground, but proud, nevertheless proud in your stubbornness, in your refusal to pretend to be someone you were not. 」
ちょっとジーンときますね。
と、こういう風に書くと面白くてぐいぐい引き込まれた章なのかというと、実はそうでもないんです。子供時代をこれだけ延々と書かれると、このままのペースと同じ文体で成長を語っていくのかと思ってうんざりすることもしばしば。正直言ってこの章が一番挫折しそうになりました。
で、Kindleでは何%読んだかも表示されるのですが、これだけ読んでまだ20%台かよ、と思い始めた頃異変が訪れます。
突然102Pで章が終わってしまい、103Pは再び一行だけ
「TWO BLOWS TO THE HEAD」
の文字。げっ、「REPORT FROM THE INTERIOR」というのは第一章の題名で、第二章があるんだ、という驚き。
まあそれはともかくとして、TWO BLOWSというのは、10歳、14歳の頃に見てそれまでに無い衝撃を受け、その後の人生に多大な影響を与えた二本の映画のことです。ですからこの章はこの二つの映画を語ることにほとんど費やされています。
オースターは第三章でも書いていますが、若い頃から映画製作への情熱も強く持っており、実際1990年代に「SMOKE」「Blue In The Face」「Lulu On The Bridge」という三作品に結実しています。
そして、小説中で映画を語ることもしばしば、それが凡百の映画評論よりもよほど巧いのです。たとえば私が彼のベスト1に推す「幻影の書」では小説中で映画を製作していますし、もうすぐ邦訳本が出る「Man In The Dark」ではかなりディープな映画評論を展開しています。(その中には小津安次郎の「東京物語」も入っていますので、映画ファンは楽しみにしておいてください。)
さてそんな彼が少年時代に最も衝撃を受けた映画を語ってくれるのですから、個人的には一番楽しんで読むことが出来ました。
最初の映画は「The Incredible Shrinking Man」(邦題:縮みゆく人間)
詳細はリンク先のMovie Walkerに書いてありますが、SF特撮映画の魁ともいえる作品です。第4章にいくつかのスチール写真が掲載されていますが、一人の人間が海上で謎の霧を浴びて段々と縮んでいく、という映画です。オースターがこれを見たのが10歳の頃。縮んでいくのが特撮だと子供心にはわかっていても、その恐怖感はそうとうだったようです。
そして同時に、縮んでいきながらも主人公は「人間」であり続けるということから、人間存在の本質とは何なのか、という疑問を抱くにいたったと述べています。深いですねえ(笑。
第二の映画は「I am a Fugitive from A Chain-Gang」(邦題:仮面の米国)
これは実在した逃亡犯の手記を基にした社会派映画の傑作で、第一次世界大戦から帰国した主人公がたどる苦渋と変転に満ちた人生を描いています。詳細に語られる内容の中でも印象に残るのは、建築関係の大きな仕事をしたくて世界大戦から帰国した主人公が逃走のために橋を爆破するというアイロニー。そして、ラストシーンで最愛の恋人と別れ再び逃亡生活に入る際に「これからどうして生きていくの?」と聞かれ,
" I steal .!"
と、たった二文字で答える痛切。オースターがこの映画を観たのが14歳、もう社会に対する十分な理解力のある年齢です。人生の不条理をこの映画から感じ取ることは容易だったでしょう。彼の小説の特徴である、主人公に次々と厄災が降りかかるというストーリーと主題の不条理性はこの映画に大きな影響を受けているのだなと納得できました。
さて、この章が終わると次に待っているのは
「TIME CAPSULE」
という第三章。経緯は省きますが、60台になったオースターの元に、大学生時代に前妻Lydiaに宛てた手紙がまとめて送り返されてきます。凡人ならもう恥ずかしくて処分してしまいたいところですが、そこはオースター。なんとこの自伝に取り込んでしまいました。
さすがに「臆面も無く」という言葉が読んでいて何度も脳裏に浮かびましたし、この作品の白眉であるという評判にはちょっと首を傾げざるを得なかったです。
彼の大学生時代の波乱万丈は前作「Winter Journal」等でも語られていますが、2年生時にパリに渡り、指導教官とそりが合わず退学を決意したものの、両親をはじめとする周囲の猛反対にあい、更にはベトナム戦争への「Draft(徴兵)」も嫌で、仕方なくとりあえずニューヨークに戻ったら大学は学生運動の真っ只中だった、という時期が描かれています。オースター・ファンなら大抵知っているこのあたりの経緯ですが、その内面を今回は晒した、というところがまあ新鮮といえば新鮮でしょうか。
たとえばコロンビア大学の学生運動と警官隊による学生排斥といえばまさに「いちご白書」の世界で、彼もそれなりに巻き込まれていますが、彼にとってはベトナム戦争などの外的問題よりあくまでも「自己」の内面の探求がその頃の一番の問題、それを身勝手と評することは簡単ですが、それも当時の学生の一つの真剣な生き方であったのでしょう。
それにしても、最後の恐ろしく長い手紙はひどい。中盤から悪友たちとのアパート探しの話が延々と続き、その中でストリップ小屋へ行っただの、友達がLSDをやってるだの、成り行きでバーで拾った女の子と寝ただのと、およそラブレターと思えないひどい内容。
精神的に不安定だったとか、衝動的に出したんだとか、あるいはラリって出したのならまだ理解できないことも無いですが、この手紙が唯一タイプライターで打って書いた手紙だというのですから恐れ入ります。(自分でも呆れてますが)
これで
"Love, Paul"
と結ばれてもねえ。。。それにしても、結局その後一度はポールとリディアは結婚するわけですから、リディアはよほど理解があったのか、彼を好きだったのか、当時の学生気質がそんな風だったのか?
とまあ、呆れてものが言えな~い(清志郎風)的に第三章で実質的にこの作品は終了します。
そんな中であえて収穫だなと思ったのは、極貧の中でいそしんでいた、彼曰く「ごく未熟」な創作活動の中にも後年の「City Of Glass」「In The Country Of Last Things」「Moon Palace」の三作品の萌芽が見られていたと語っていること。私の大好きなこの三作品が彼の原点であったということはとても嬉しかったです。
第四部は冒頭にも述べたように気楽にこの作中の内容に関する写真が集められており、気楽に楽しめます。というか、その該当する場所に適宜挿入してほしかったという気もします。
以上、奇抜で大胆なしていささか散漫で唐突な自伝ではありますが、とりあえずポール・オースターの作品ではありますから、クリアいたしました。ああしんど。